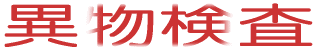■試薬というのは薬品のことです
|
異物をよく観察して、異物の特徴をつかんだら、異物が何かを調査するために、薬品を加えて色が変わったり、溶けたりするかどうかを観察します。
異物に応じて使う薬品も変わってきますし、薬品を使うと異物が変質してしまいますから、1つの薬品に異物全部を入れたら絶対にダメ。
メスや針などを使って、小さくしてから試験します。
異物が小さいと、さらに細かくしてから試験するので、目視で変化を見られない場合があります。そこで、実体顕微鏡や光学顕微鏡などを併用しながら試験をすることが多いのですが、一瞬で溶けてしまうものなどもあるので要注意。
変化を見逃さないように、神経を研ぎ澄ませて観察しないといけませんし、また細い繊維系の異物だと鼻息で飛んでいってしまいますから、マスクをしていても息を止めてしまいます。(笑)
|
|
|
デンプン反応試験
 異物にデンプンが含まれているかどうかを 異物にデンプンが含まれているかどうかを
調べるための試験です。
ヨウ素-ヨウ化カリ溶液を加えて、
試料が紫色に変色するかどうかを確認します。 |
デンプンを含むもの
|
・ジャガイモなどの芋類 |
・増粘多糖類などの添加物 |
|
・小麦粉、米などの穀類 |
・接着剤(のり)の一部 |
|
・小豆、ソラマメなどの豆類 |
・製紙の一部 |
|
|
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
ニンヒドリン反応試験
 異物にタンパク質やアミノ酸が含まれているかどうかを調べるための試験です。 異物にタンパク質やアミノ酸が含まれているかどうかを調べるための試験です。
ニンヒドリン試薬を加えて加熱し、試料が青紫色に変色するかどうかを確認します。
この方法は、警察の鑑識で、紙に付いた指紋を検出するためにも用いられている方法です。 |
アミノ酸やタンパク質を含むもの
|
・肉、骨、軟骨などの組織 |
・皮膚片(フケなど)、皮脂 |
|
・卵、乳製品 |
・ソース等の加工食品 |
|
・種子胚、豆類 |
・グルテンなど |
|
|
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
脂質呈色試験
 異物に油脂や脂肪などが含まれているかどうかを調べるための確認試験です。 異物に油脂や脂肪などが含まれているかどうかを調べるための確認試験です。
ズダン試薬を加えて、油分が橙色に変色するかどうかを確認します。 |
油分や脂質を含むもの
|
・サラダ油、バターなどの油脂 |
・皮脂 |
|
・乳製品 |
・ソース等の加工食品 |
|
・アーモンドなどのナッツ類 |
・機械油等 |
|
|
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
鉄粉の呈色試験
 異物に鉄を含む金属が含まれているかどうかを調べるための確認試験です。 異物に鉄を含む金属が含まれているかどうかを調べるための確認試験です。
酸とフェロシアン化カリウム溶液を加えて調べます。もし鉄が含まれていたら、鮮やかな青色を示します。 |
鉄を含む金属粉が付着・混入しやすい異物
|
・製造機器の汚れ |
・鉄板のコゲの表面 |
|
・エージレスなどの脱酸素剤 |
・グリース類 |
|
・工具類のサビ |
・土砂など |
|
|
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
ルミノール試験
 異物が血液かどうかを調べるための確認試験です。 異物が血液かどうかを調べるための確認試験です。
ルミノール試薬を加えて紫外線ランプで発光を確認調査します。もし血液が含まれていたら、写真のように暗所で発光します。 |
血液が付着しやすいもの
|
・ダンボールや包装袋の外側 |
・噛み跡の近く
(特に冬場では、唇が切れたりアカギレ由来の血液付着が多い) |
|
・肉・魚製品のトレイ |
|
|
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
カタラーゼ試験
 異物が加熱されているかどうかを調べるための簡易試験です。 異物が加熱されているかどうかを調べるための簡易試験です。
生物に含まれている酵素「カタラーゼ」があるかどうかを確認するため、カタラーゼ試薬(過酸化水素水+α)を加えて気泡の発生を確認します。
詳しい説明はコチラ → 07 加熱されているかどうかを調べる方法
|
カタラーゼ試験で気泡が発生するもの
|
・加熱されていない虫 |
・加熱されていない生物全般 |
|
・生肉や生魚、お刺身 |
・細菌やカビなどの微生物 |
|
・加熱されていない毛の毛根 |
|
|
|
カタラーゼ試験で加熱の有無を判別できないもの
|
・植物片、木片などは、水を加えても気泡が発生するものがあるので、判別できないことが多い |
・発酵食品に混入していたものは商品に含まれている乳酸菌や酵母などの微生物が反応してしまうので判別できない |
|
・死亡して4ヶ月以上経過している生物は酵素「カタラーゼ」が失活しているので加熱されているかどうかわからない |
・腐敗しているもの、カビが生えているものは、細菌やカビなどの微生物が反応してしまうので判別できない |
|
・毛根が無い動物毛、髪の毛など |
|
|
|
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
繊維溶解・染色試験
 繊維の種類を簡易定性する方法です。 繊維の種類を簡易定性する方法です。
様々な試薬や顔料等を加えて、繊維が溶解するかどうか、染色されるかどうかなどの特徴を観察して繊維の種類を推測します。
|
繊維の種類と用途
|
・ポリエチレン、ポリプロピレン
梱包紐や釣り糸、排水溝用ゴミネットなどに利用 |
・アクリル
セーター、毛布などに利用 |
|
・ポリエステル(PET)
衣類、雑貨、じゅうたんなど多くのものに利用 |
・綿
タオル、衣類、寝具など多くのものに利用 |
|
・ナイロン
ストッキング、台所用スポンジの研磨部分などに利用 |
・レーヨン
洋服の裏地などに利用
|
|
|
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
その他の試薬反応
例えば、塩酸を加えて気泡が発生する炭酸カルシウムやリン酸カルシウムが入っているかどうかを調べたり、有機溶媒を加えて試料が変形するかどうか、など、試験に応じて適した試薬を用います。
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
 例の異物 (前のページ参照) に様々な試薬を加えて反応させたところ、 例の異物 (前のページ参照) に様々な試薬を加えて反応させたところ、
・シクロヘキサノンという有機溶媒で溶けました
・希塩酸を加えると勢いよく気泡が発生しました
このことから、異物の結晶は樹脂系の物質で、炭酸カルシウムなどの塩酸を加えると気泡が発生する物質が含まれている可能性が高くなりました。
|
|
|
|
|
 |
異物検査の方法

|
|
|
|
|
|
|
|
機器分析
(現在工事中) |
| EPMA-EDS |
| FT-IR |
| HPLC |
| GC-MS |
| その他 |
| カタラーゼ試験 |
|
|
|
|
|
|