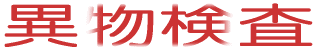■鑑別するためには色々な調査を必要とします
|
試薬試験で反応出たから、すなわち○○・・・と言えないところが異物検査の難しさ。色々な試験を複数行い、総合的に判断する必要があります。
それは比重を調べたり、燃焼したりというごく初歩的なテストから、毛髪を調べたり昆虫同定を行ったりという専門的な知識を有するものまで、さまざま。
異物検査には、多くのテクニックと幅広い知識が必要なのです。
|
|
比重試験
 樹脂片(プラスチック片)のような固形異物を 樹脂片(プラスチック片)のような固形異物を
簡易的に分類する方法です。製造現場などで
の簡易判定に利用できます。
この方法は、樹脂や固形物の種類によって
比重が異なることを利用しています(一般に
樹脂の比重は0.8〜2.0)。
最近では樹脂の特性を高めるために様々な添加剤が含まれていることから、比重だけで固形異物の種類を推測することはできませんが、
・水(比重1付近)
・15%食塩水(塩化ナトリウム水溶液、比重1.15付近))
に浸して、異物が浮遊するか沈降するかを観察するだけで、樹脂の種類を大きく分類することはできます。 |
水に浮くもの(一例)
|
・ポリエチレン
(HDPE, LDPEなど) |
・EVA樹脂 |
|
・ポリプロピレン |
・ブタジエン樹脂 |
|
|
|
水にも15%食塩水にも沈むもの(一例)
|
・PVC(ポリ塩化ビニル, 塩ビ) |
・ナイロン(ポリアミド) |
|
・メタクリル樹脂
(アクリル樹脂の一種) |
・PET
(ポリエチレンテレフタレート) |
|
・ポリカーボネート |
・金属 |
|
・ガラス |
・毛 |
|
・大部分の土砂
(一部軽石など浮くものもある) |
・ゴム |
|
|
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
燃焼試験
 異物を燃焼させて、以下の項目を確認します。 異物を燃焼させて、以下の項目を確認します。
・燃え方、燃えやすさ
・炎の色や形状
・燃焼時の臭い
・炎を遠ざけた時の特徴
・燃えダレの有無
・煙の色
・燃えた後の形、樹脂の曲がり具合
燃焼試験はとても多くの様々な情報が得られますが、燃えると異物が変質したり溶解したり無くなったりするので注意が必要です。カタラーゼ試験と同様に最終試験として行います。
|
燃焼試験の一例
|
・ポリエチレンの場合
燃えやすく、炎を遠ざけても燃える。燃えて液状になる。
炎の先端は黄色っぽく、末端は青色がかっている。
燃焼時の臭いはロウソク臭がする。
煙はほとんど出ない。かすかに白色。
燃焼後は熔融(直火で加熱されて熔けること)した後固まる。
|
|
・PET(ポリエチレンテレフタレート)の場合
ポリエチレンに比べると燃えにくく、炎を遠ざけると徐々に消える。
煙は黒煙を上げる。
燃焼時の臭いは芳香臭がする。
燃焼後は熔融した後固まる。ひび割れがあったり、膨れた部分
が見られたり色が変化したりする。
|
|
・複合樹脂PE/PA(ポリエチレンを主体としてポリアミドを含む)の場合
ポリエチレンに比べると若干燃えにくい。
煙はほとんど出ない。
燃焼時の臭いはロウソク臭がする。
燃焼後は熔融した後固まる。色はわずかに淡褐色になる。
ラミネートフィルムの場合は、必ず片側一方向に曲がりながら
熔融する。
|
|
|
|
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
毛髪鑑別
 毛髪が人の毛なのか獣の毛なのか、 毛髪が人の毛なのか獣の毛なのか、
獣の種類は何かなどの調査をするために、
次の項目を確認します。
・全体の長さ、太さ、硬さ
・毛先、毛根の特徴
・色、および色の変化
・毛の断面の形
・毛髄の太さ(毛髄の断面比率の測定)や毛髄の形態
・毛の表面の毛小皮紋理(キューティクル)の観察
毛髪の鑑別には、目視観察、顕微鏡観察を行い、特徴を調べていきます。また、キューティクルの観察には、スンプ法というキューティクルの転写法と走査型電子顕微鏡による表面観察の2つの方法がありますが、異物総研では安価で早く結果が出せるという理由から、スンプ法を主に使用しています。
毛髪からは、血液型の鑑定やDNA検査による異同識別(同一人物の毛かどうか)、親子鑑定などの情報が得られますが、現在のところ、弊社では異同識別や親子鑑定に関わる業務については行っておりません。 |
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
昆虫鑑別
 昆虫鑑別は、虫の種類によって調べ方が異なります。もちろん見た目や色だけではなく、それぞれの種類に合わせた部位の調査が主になります。 昆虫鑑別は、虫の種類によって調べ方が異なります。もちろん見た目や色だけではなく、それぞれの種類に合わせた部位の調査が主になります。
例えば、ハエやカなどの双翅目(ハエ目)では翅のライン(翅脈)が重要なポイントとなります。
日本での文献入手が難しい昆虫に対しては、大学で昆虫学を専門に研究されている先生方の力をお借りして同定を行うこともあります。 |
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
植物種調査
 異物として混入していた植物が何かを調査します。 異物として混入していた植物が何かを調査します。
しかし、植物の種類同定は植物の全体(根、茎、花、葉の付き方)などが必要で、一部分だけでは調べられないことも多くあります。
そのため、植物種の調査は
・異物が市販されている「野菜」かどうか
 ・原料に入っている調味料かどうか ・原料に入っている調味料かどうか
・種の調査
・落ち葉、枯葉の調査
など、文献や対照品が入手できるものに限られます。
ちなみに、写真上は異物の写真、写真下はピーマンの表皮の写真です。 |
|
| ページ上部に移動 ↑ |
|
|
|
|
 |
異物検査の方法

|
|
|
|
|
|
|
|
機器分析
(現在工事中) |
| EPMA-EDS |
| FT-IR |
| HPLC |
| GC-MS |
| その他 |
| カタラーゼ試験 |
|
|
|
|
|
|